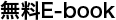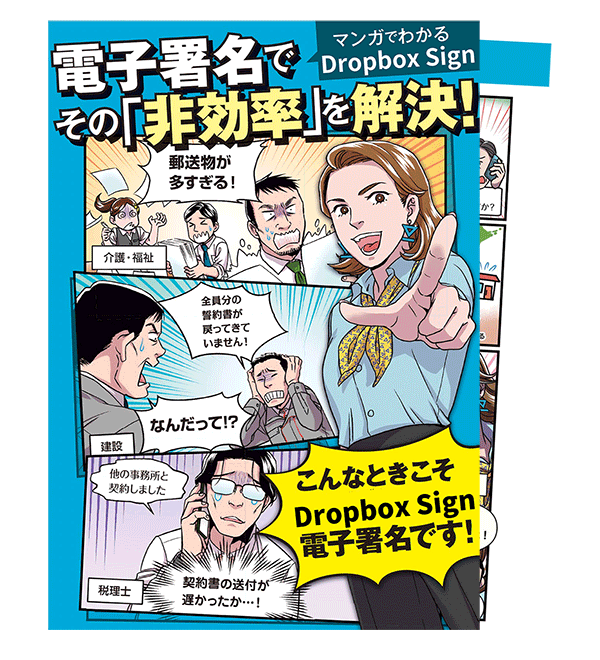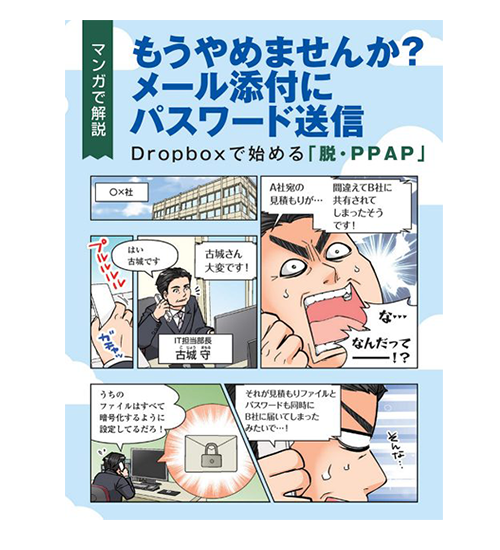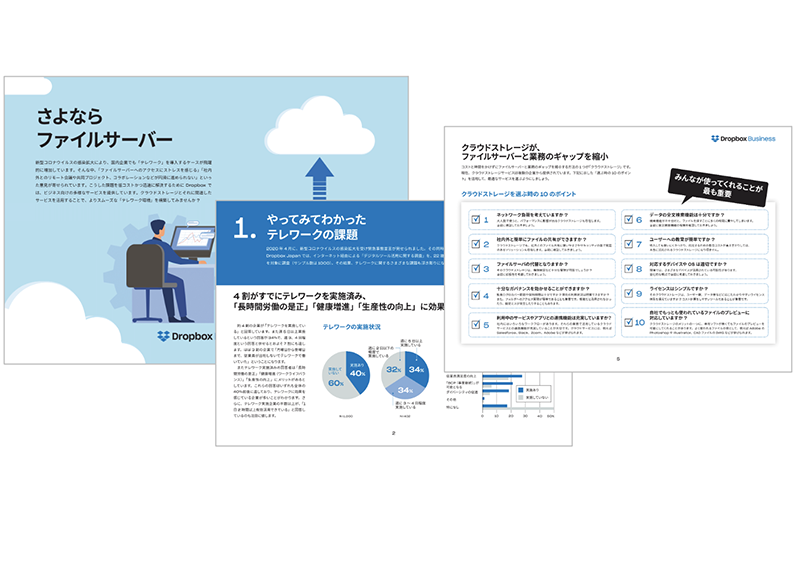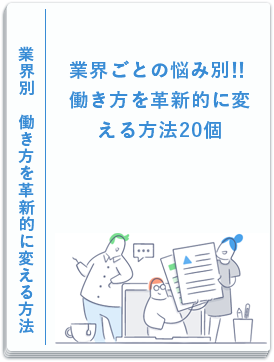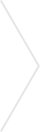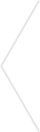2002 年公開のネオノワール映画「マイノリティ リポート」で、トム・クルーズ演じる主人公ジョン・アンダートンが無数の映像の中から犯罪の証拠を見つけ出そうとするシーンがあります。ここで主人公が使っていたのは、私たちがよく知るデスクトップ パソコンでもノート パソコンでもありません。アーチ型のホログラフィック スクリーンに映し出された映像を、マウスではなく、発光するデータ グローブでスワイプをしていました。犯罪の証拠を捉えると、複雑なハンド ジェスチャーで目的の映像を取り出します。
空中のホログラム映像を操作するというアイデアは、劇場公開から 18 年が経過した現代でさえ SF のように感じてしまいます。しかし、これはフィクションではありません。
UI 研究者のジョン・アンダーコフラー氏は、同作のためにジェスチャー型言語システムと、それを扱うコンピュータ インターフェースのプロトタイプを設計、開発しました。作品の中で主人公が画面をつまむと映像が一時停止し、3 本の指をひねると映像が早送りされます。本物のように見えるシーンですが、それもそのはず。あのインターフェースは本物だったのです。
「マイノリティ リポート」がプレミア公開されると、アクセンチュアやウェルズ・ファーゴ、富士通など Fortune 500 に名を連ねる複数の企業が、映画の中で使われていたインターフェースを自社製品向けに作ってほしいとアンダーコフラー氏のもとに依頼が来た、という出来事がありました。当時の状況を考えると、無理もないことです。テクノロジーが劇的な進化を遂げる一方、仕事に使われるユーザー インターフェースは、数十年間ほとんど進歩していなかったからです。
私たちが今使っているノート パソコンは、1980~1990 年代のデスクトップ パソコンと比べて数十万倍も高性能でありながら、インターフェースはほとんど何も変わっていません。
むしろ、急速に消えつつある時代に合わせて設計されたものだと考えると、状況は後退していると言えるかもしれません。今のインターフェースは、対人を基本とする仕事環境、つまり同僚との間で多くの対人コミュニケーションが発生する環境を前提としています。しかし今は、テレワークによってナレッジワークの仕事環境が分散化へと大きく変化してきており、従来の職場は消えつつあります。
私たちがテクノロジーをどう扱うのかは、私たちがどう仕事をするのか、ひいては仕事を「どう考えるか」を決定付けます。代わり映えのしないインターフェースは、人間の潜在能力の足かせとなり、創造性を阻害し、問題解決を妨げかねません。
インターフェースは、テレワークという新しい働き方に合わせて進化しなければなりません。さもなければ、共同作業は困難となり、私たちの考える力を束縛して、人間の進化を押しとどめてしまう結果になるでしょう。
インターフェースが相互作用のあり方を決める
現代の技術的な進歩のほとんどは、コンピュータ化によって成し遂げられたものです。人工知能から遺伝子治療、宇宙飛行、再生可能エネルギーに至るまで、技術革新の多くは、コンピューティング能力の圧倒的な成長が大きく貢献しています。しかしコンピュータ化は、私たち人間に、ある問題を突きつけています。私たちは、3 つの次元や肉体的な感覚などで構成される物理的な世界を理解できるまでには進化していますが、デジタルの世界は物理的な世界と似ている部分がほとんどないのです。
「理解可能」な物理世界と「不可解」なデジタル世界。2 つの世界をつなぐ架け橋がインターフェースですが、その代表例がグラフィカル ユーザー インターフェース(GUI)と呼ばれるものです。
Apple が Macintosh コンピュータで GUI を取り入れたのは 1980 年代初頭のことです。Macintosh にはモニター、キーボード、マウスが用意されており、ユーザーはウィンドウという 2 次元のインターフェースを介してシステムを操作します。40 年前、この仕組みは革新的と評されました。しかしそれ以降、GUI のイノベーションは遅々とした歩みしか見せていません。
「ゲームを除くほとんどの用途における汎用ユーザー インターフェースは、1984 年以降、大きくは発展しておらず、飛躍的進歩と言えるような変化は起きていません」と、アンダーコフラー氏は VentureBeat の 2018 年の記事で述べています。「1984 年というのは、Apple がコマンドライン インターフェースから GUI、つまりグラフィカル ユーザー インターフェースに移行した年です。それ以降に登場したすべてのユーザー インターフェースは、GUI の派生形に過ぎません。」
私たちが今使っているインターフェースの多くは、物理世界のことを頑固なまでに理解してくれません。デジタルのツールやサービス、プラットフォームは、単独で機能しないため、これは重要な問題です。個々のインターフェースがその周辺の世界とどう融合するのか、あるいはしないのか。そこに注目する必要があります。
「経験における背景情報は、その経験の中でどのような知識や理解が形成されるかを決定付ける際に大きく影響する」と、エジンバラ大学の研究者らは指摘しています。「コミュニケーションの 93 % は非言語要素である、『メディアはメッセージである』、『テクスト外なるものは存在しない』というのは、よく言われることです。」
クリスチャン・フレクサ氏、アレクサンダー・クリッペル氏、ステファン・ウィンター氏からなる研究チームは、地図ソフトウェアのインターフェースに関するさまざまな例を紹介しています。この論文では、それぞれのシナリオにおいて、空間環境、デジタル再生、そしてユーザーの関係性を操作。十分な文脈が得られる場合、ユーザーは、現実世界またはデジタル地図を見るだけでは解決できない問題を解決できると同チームは主張しています。
インターフェースに関する失敗は何かの「欠如」から生じるだけではありません。意図を持ってデザインされた機能がもたらす意図しない結果によって生じることもあります。コンピュータ科学者から技術哲学者に転身したジャロン・ラニアー氏は、ワールド ワイド ウェブにおける相互作用のあり方を繰り返し批判してきました。たとえば Scientific American 誌では、ユーザー インターフェースやログインなどウェブの主な構成要素は「分断化の原因になり他者に悪用されている」と述べています。
私たちがテクノロジーをどう扱うかは、私たちがどう仕事をするか、ひいては仕事を「どう考えるか」を決定付けます。代わり映えのしないインターフェースは、人間の潜在能力の足かせになります。
中でも、匿名が批判目的で乱用されているとラニアー氏は指摘します。ソーシャル メディアやニュース フォーラムなど、ほとんどのウェブサイトではユーザーが匿名でコメントできるようになっています。このためインターフェースを通せば匿名の仮面をかぶってコミュニケーションすることができ、一部のユーザーが人目を気にせず誹謗中傷や暴力的な意見を投稿する要因になっています。「荒らし行為は、個別の事象が連なったものではなく、オンラインの世界の現状そのものである」と、ラニアー氏は自著「人間はガジェットではない」で述べています。
アンダーコフラー氏やラニアー氏などのテクノロジー分野の有識者と、フレクサ氏、クリッペル氏、ウィンター氏などの学術界の研究者は、デジタル世界と「どのように」相互作用するかが重要だという点で意見が一致しています。それは、情報消費のあり方に影響を与え、情報をどのように処理するかを規定するものだからです。そして全員が、インターフェース設計はまだ始まったばかりの分野であるという認識を共有しています。
すばらしい新世界
GUI は依然として主要なユーザー インターフェースとして利用されていますが、研究者がその周辺領域を模索していないわけではありません。 たとえばラニアー氏は、キャリア初期のかなりの時間を仮想現実の先駆的な研究に費やしており、「バーチャル リアリティ」の命名者とされています。
同氏はかつて、仮想現実というインターフェースが芸術とコミュニケーションの分野に革新をもたらすと考えていました。遠方にいる人と話をする際には電話を使うのではなく、仮想現実の世界で、互いに「奇妙でエキゾチック」なアバターの姿で対面するようになると予想していたのです。
「驚くべき認識能力と多様なスタイルを持ち、それぞれ隔絶した空間で生活する人々、というイメージを思い浮かべていました」とラニアー氏は 2011 年に The New Yorker で語っています。
仮想現実に関するラニアー氏のビジョンは、まだすべて実現するまでには至っていませんが、「拡張現実」という隣接分野における同氏の研究活動はすでに実を結んでいます。同氏は Microsoft に所属していた数年間、Kinect というモーションベースのゲーム システムの開発に従事していました。このシステムでは、一般的なコントローラーでビデオ ゲームを操作するのではなく、ユーザーの現実世界での動きをゲーム内のキャラクターに適用します。たとえば、ユーザーが現実世界でジャンプすれば、画面上のアバターもジャンプするのです。ラニアー氏は、この成果について「Kinect は考えることの意味を拡張した」と述べています。
この物理空間とデジタル空間の関係性は、アンダーコフラー氏が取り組んできたテーマでもあります。
「問題の鍵となるのは、『空間』という 1 つのシンプルな単語、あるいは『現実世界の幾何学』という 1 つのシンプルなフレーズです」と、アンダーコフラー氏は 2010 年の TED Talk で語っています。「コンピュータと、それに指示を与えるプログラミング言語は、空間という概念にひどく無頓着です。現実世界の空間というものを理解してくれません。」
アンダーコフラー氏が設立した企業 Oblong が提供する Mezzanine などのプラットフォームは、物理空間と仮想空間の断絶という問題を解決します。たとえば Mezzanine では、空間の 2 次元表現ではなく、3 次元表現でテクノロジーを扱うことができます。
ある企業は、貯水場の設計とシミュレーションに Oblong のテクノロジーを利用しています。エンジニアは、キーボードとマウスではなく、自分の手を使ってシステムを操作します。たとえば、水源を北に 500 メートル移動したければ、「マイノリティ リポート」に出てくるようなデータ グローブを使って水源の仮想モデルを持ち上げ、目的の場所に移動することができるのです。
また、Oblong のエンジニアであるピート・ホーキンス氏は、Excel シート上の地震活動データを、Mezzanine に投影した地球の上に視覚的に表現しています。震源の深さの違いを色の違いで表し、活動の大きさをドットの大きさで表現するといった具合です。
「私たちが目指しているのは、データを単なる行列ではない形で表現することです」とホーキンス氏は説明します。「Excel では、データに対してできることがごく限られてしまいます。これを人間にとってわかりやすい方法で表現することで、もっと人間らしいニュアンスを込めることができます。」
インターフェースが直面しているもう 1 つの課題が共同作業です。現代社会では、たいていの仕事が多くの人の関与で成り立っています。それにもかかわらず、コンピュータは依然として孤立したまま。ネットワークを介して複数のコンピュータを連動させることはできても、根本的には独立した機械です。
デスクの間を物理的に移動して、同僚と同じディスプレイを見ることのできるオフィス環境では、これは大きな問題になりませんでした。しかし、テレワークの普及によって仕事環境の分散化が進んだ今、この方法で問題を解決することはもうできません。画面共有機能やコラボレーション用のソフトウェアでそのギャップを埋めようとしても、期待どおりの成果は得られないのが実情です。
このテレワークの時代に対応するためには、実験的なインターフェースを用意し、従来のような人間とマシンの 1 対 1 の関係を超えて拡張していく必要があります。社員ごとに個別のデジタル空間を用意するのではなく、社員同士が同じ空間で共同作業してコンテンツやアイデア、仕事を共有できる、大規模な共有ワークスペースが必要になるかもしれません。
36 年に及ぶ呪縛を乗り越える
Apple の GUI が登場したのは 1984 年、今から 36 年も前のことです。Z 世代(1990 年代半ば~2010 年頃に生まれた世代)の人に、GUI を搭載した最初の Apple コンピュータである Macintosh 128K を渡したとしても、おそらく使い方を理解することができるでしょう。インターフェースがわかりやすく使いやすいからだと思う人がいるかもしれませんが、アンダーコフラー氏やラニアー氏などのインターフェース研究者に言わせれば、それが可能なのは、現代のインターフェースが 1984 年当時のインターフェースの高解像度版に過ぎないからなのです。
私たちは、インターフェースを刷新するでも試行錯誤するでもなく、とりあえず使えるものを、「使えるから」という理由で使い続けてきました。
しかし、単に「使える」というだけでは不十分です。特に、テレワークへの移行が一気に進もうとしている現在ではなおさらです。テレワークが当たり前の世界では、私たちが使うインターフェースは人間的なつながりを育むものでなければなりません。人間は社会的な動物です。完全に孤立した状況で仕事をしていては、成長し、イノベーションを実現し、幸せを感じることは難しいでしょう。
「人間は、ものを作る生き物です」とアンダーコフラー氏は話します。「私たちが使う機械は、ものを作るという作業を手助けするものであるべきですし、そのイメージの元に作られているべきなのです。」