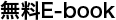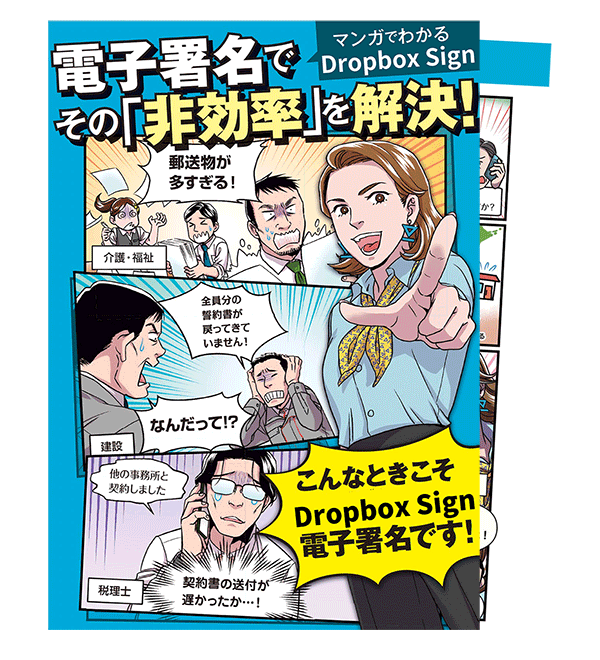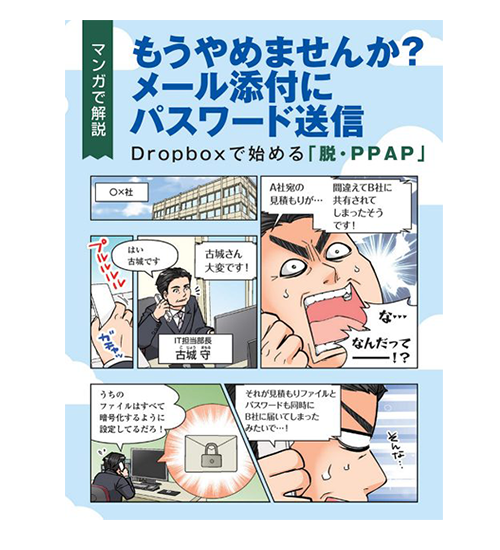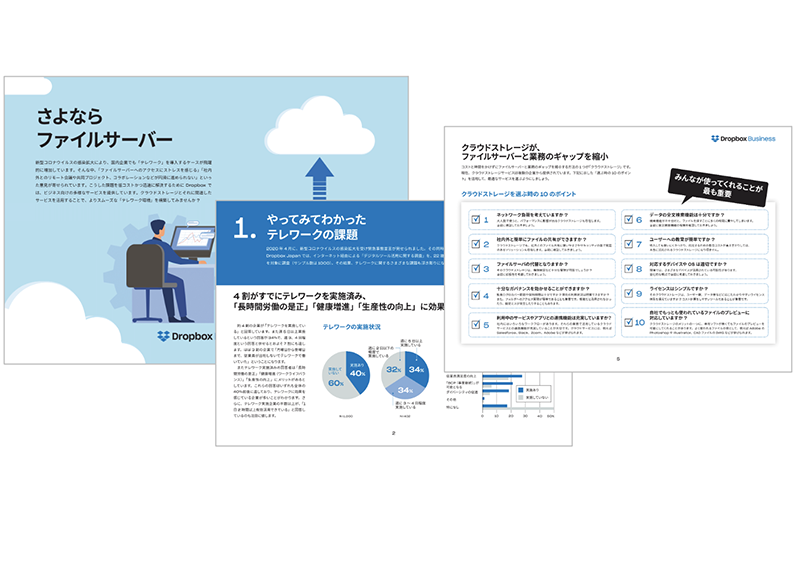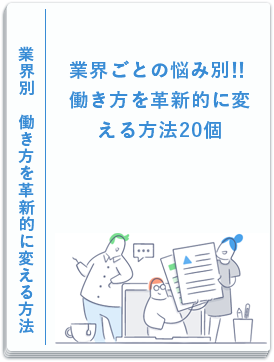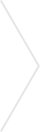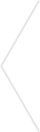トーマス・エジソンはかつて、ビジネスにおける成功の 90 % は努力の賜物であると述べました。また、人生における成功の 80 % は、「その場に現れることだ」と述べた人もいます。具体的な数字はさておき、こうした考えは、仕事に関する私たちの集合意識にすり込まれているのではないでしょうか。
朝早くに仕事を始め、夜遅くまで働くことを自慢する人は少なくありません。けがや病気を押して出社する人もいるでしょう。「1 日 8 時間の勤務時間内はいつでも対応できます」と周囲に請け負っている人もいます。
時間は、物事を測る尺度として確かに便利です。時間は具体的な概念であり、1 秒は間違いなく 1 秒、1 時間は間違いなく 1 時間です。記録するのも比較するのも簡単で、管理職は社員のタイム カードを確認すれば、各自が「どれだけ仕事をしたか」を一目で把握できます。
過去数十年間、時間は、社員にとって安心できる評価手段として機能してきました。これは特に、「何があっても姿を見せる」ことを重視する企業で言えることです。社員は、自分に何が求められているかを理解し、それを達成する手段は「職場に行くこと」だと認識していました。
しかしここへ来て、状況が一変しました。パンデミックで多くの人がオフィスを追われてテレワークを余儀なくされ、現在に至るまでその状況が続いているのです。たくさんの社員が今もそれぞれの自宅で仕事をする中、管理職は、社員がどれだけの時間を仕事に費やしているのか把握できずにいます。社員の姿が見えなくなったことで、時間という評価手段が役に立たなくなりつつあるのです。
私たちは、何世代にもわたって「姿を見せること/姿が見えること」に依存してきました。姿を見せればそれだけで問題なしと判断され、不調を抱えた状態で出社し生産性を発揮できないことを意味する「プレゼンティーイズム(疾病就業)」という言葉まで生まれました。しかし、多くの人がオフィスに出社しなくなっては、その評価基準は何の役にも立ちません。
では、今は何を重視すべきなのでしょうか?
オフィス勤務の問題点
Economist Intelligence Unit が最近実施した調査によると、パンデミック以前、オフィス勤務の一般的な社員は、集中を妨げられることによって勤務時間の 3 分の 1 近くを失っていました。この事実は、これまで隠されていたある真実を明らかにしています。過去数十年もの間、多くの企業は社員に通勤を求めていたが、それによって多くのものを失っていたということです。
その原因の多くはオフィスの物理的な構造にあります。最近のオフィスは、仕切りのないオープンな空間になっているケースが多く、それが集中を妨げる主な要因になっているのです。米カリフォルニア州立大学イースト ベイ校で経営学の准教授を務めるリン・ボウズ=スペリー博士は、パンデミック前のオフィス勤務では自身の集中を妨げるさまざまな要因に悩まされていたと話します。大声で話しながら廊下を行き来する学生たち、大音量で音楽を流して授業の邪魔をする隣の教室の職員、不意にやってきては作業の邪魔をする同僚などです。
「こうした経験の一つひとつに集中を妨げられ、時にはもうたくさんと叫び、引きこもってしまいたいほど追い詰められていました」と博士は当時を振り返ります。「学部会議でも、出席しながら心ここにあらずの状態になったり、強いストレスで会議を欠席したりすることがありました。」
ボウズ=スペリー博士の経験は特別なものではありません。Economist Intelligence Unit の調査でも、オフィスで働くナレッジワーカーの集中を妨げる最大の要因として、「仕事に関連する、同僚からの対面での声かけ」(全回答中の 34 %)が挙げられ、次いで「仕事関連のメールの確認と返信」(同 29 %)が挙げられています。サルトルの有名な一節「地獄とは他人のことだ」になぞらえれば、「集中の妨げとは他人のことだ」とでも言うべき状況です。
この調査結果は、オフィス勤務の経験がある人々にとって意外なものではないでしょう。オフィスで働いたことがあれば、誰もが勤務時間中、絶え間なく作業を妨げられ、遅々として仕事が進まず、ほとんど何もできなかったという 1 日を過ごした経験があるはずです。しかし、その深刻な結果を理解している人は決して多くありません。あまりにも頻繁に集中を妨げられるナレッジワーカーは、「実際に生産性を上げる方法」ではなく、「生産的に見せる方法」を学んでしまうのです。
これは、企業の業績に甚大な影響を及ぼします。社員が勤務しながら実質的に働いていない時間が積み上がっていくのですから当然です。こうして米国企業が失っている生産性は、実に年間 3,910 億ドル相当に上ります。無為な日々が過ぎていく中で、イノベーション、アイデア、チームの士気が失われていくのは言うまでもありません。
しかし、先ほど少し触れたように、テレワークはこの問題を解消する手段になり得ます。
画面の向こうでの働き方
2020 年に入ったばかりの頃、テレワークはほとんどの社員にとって無縁の働き方でした。米労働省労働統計局が実施した 2019 年の調査によると、勤め先の会社がフレックス オフィス制度またはテレワーク制度を用意していると回答した就労中の一般米国人は、わずか 7 %。しかしパンデミック初期には、この数字が 42 % に跳ね上がります。
あまりにも頻繁に集中を妨げられるナレッジワーカーは、「実際に生産性を上げる方法」ではなく、「生産的に見せる方法」を学んでしまうのです。
同じ頃、新たにテレワークで仕事を始めた多くの社員は、環境の急激な変化に直面しました。
「多くの社員はこれまで、自分がどのような方法で評価されるのかをはっきりと理解していました」と語るのは、米国心理学会の従業員支援諮問委員会の元共同委員長で、現在は民間の医療機関 JourneyPure で最高臨床責任者を務めるブライアン・ウィンド博士です。「その場にいることは、会社によっては業績評価の一部になっていたでしょうし、仕事内容についてのフィードバックをオフィスにいる間に受けることもよくありました」と同博士は指摘します。
今では、管理職はレポートやデザイン、分析などの成果だけに目を向ければ済むようになりました。これは、会社、チーム、社員など、すべての人にとって良いことかもしれません。社員にしてみれば、使い慣れた毛布をはぎ取られてしまった気分かもしれませんが、この新たな働き方に適応することは、自身の可能性を広げる絶好の機会になり得ます。
CareerPlug でメディア リレーションズ マネージャーを務めるローレン・トッレグロッサ氏は、この一大転換に感謝しています。確かに管理職にとって、部下たちが何をしているのかわからないという事態は大惨事につながりかねない危険な状況だと同氏は話します。それでも、目的が明確で、社員一人ひとりの裁量が認められている限り、この変化は社員の能力や意欲を高めるものになっているはずだと言います。
「私は、勤務時間ではなく成果が重視される社会に変わったことをありがたく思っています」とトッレグロッサ氏は言います。「勤務時間ばかりが重視されていたら、もっとスマートに、もっと効率よく生産的に働こうという動機づけにはなりません。悪くすると、車輪を空回りさせているだけの社員ばかり、ということになりかねません。」
しかし、何世紀も前から続く、時間重視の働き方から脱却するのは簡単ではありません。ウィンド博士は、まず期待事項を管理職とすり合わせるところから始めるべきだと助言します。社員と管理職が 1 対 1 で話す機会を作り、管理職が社員に求めることを確認し、社員がテレワークの一環として習得すべきスキルや特性、達成すべき目標について話し合います。これらの点を管理職から明確にしておくと、社員は自身の業績やその評価方法をより正確に理解することができます。それだけでなく、社員に自己評価を促すこともできます。
「社員は、その日に達成すべき明確な小目標を立てることもできます」とウィンド博士は話します。「こうした小目標をクリアすることは、達成感の獲得につながります。そして管理職から定期的にフィードバックを得て、これらの目標がチームの目標や会社の目標に合致しているかどうかを確認すれば、自身の仕事振りが正しいかどうかを判断できます。」
社員に対し、自分自身の仕事についてより深く考えることを求める声もあります。以前であれば、時間ベースでタスクやプロジェクトを作成するという方法も有効でしたが、テレワーク環境で働く社員は、いかにして成果を最大化するかを考えなければなりません。Resume.io で最高人事責任者を務めるロルフ・バックス氏は、自分自身の役割と日々の仕事を改めて見直すことを提案します。
「そのためにはマクロレベルで考えることが必要です。しかし多くの人は、そうした考え方に慣れていないか、そのための訓練を受けていません」とバックス氏は言います。「自分に問いかけてみてください。自社の中核事業は何だろうか、その成功に貢献するために自分にできる仕事は何だろうか、と。その仕事を毎日、毎週こなすことができれば、あなたの上司は満足し、その上の上司、さらにその上の上司も満足することになるでしょう。」
ウィンド博士やバックス氏のような専門家も、仕事環境の一大変化が苦痛を伴うものであることを認めています。何しろ、長い間定着していた習慣を捨て去ろうというのですから、それも当然です。しかし、その苦痛を乗り越えることによって得られる成果は、個人のスキル開発やチームの士気、ひいては会社の業績に好影響をもたらすはずです。
「成果だけに集中することは、結果としてプレゼンティーイズムを排除することにつながるのではないでしょうか」とバックス氏は話します。「多くの組織、特に、経営陣や管理職が年配で、テレワークやその潜在的な効果に懐疑的な組織では、テレワーカーを評価する唯一の基準として、収益に与える短期的、中期的な影響だけに着目することになるでしょう。」
一人ひとりがポテンシャルを最大限に発揮する好機
テレワークが普及する今は、皆が「仕事」とは何かを見直し、職場における集中について再考する絶好の機会です。私たちに必要なのは、生産性と時間という 2 つの概念を切り離すことです。その上で、成果、つまり「報酬の支払い対象となる仕事」を中心に思考の方向性を改める必要があります。それは苦痛と困難を伴う経験になりますが、時間という呪縛から解き放たれることで、私たちは皆、それぞれの役割における可能性を広げることができます。自分自身の価値を時間という尺度で測るのではなく、進歩と変化、そして成果に目を向け、それに適応していきましょう。
外的な要因による作業の中断や集中の妨げが私たちの勤務時間を奪っていくことは、今後はなくなります。私たちは、自分自身のすべてを、優れた成果を出すために欠かせないスキルと知識の習得、改善に注げるようになるでしょう。
この一大変化は、生産性や効率性を高める機会になるだけではありません。日々の仕事を、もっと有意義で魅力的な、やりがいのあるものとするための機会でもあるのです。