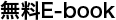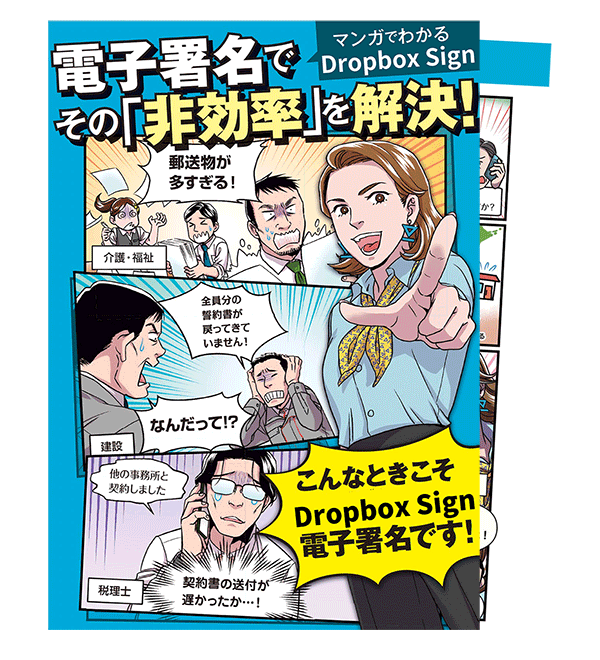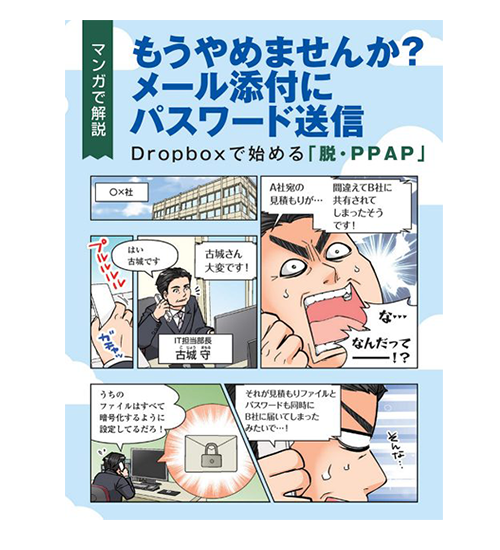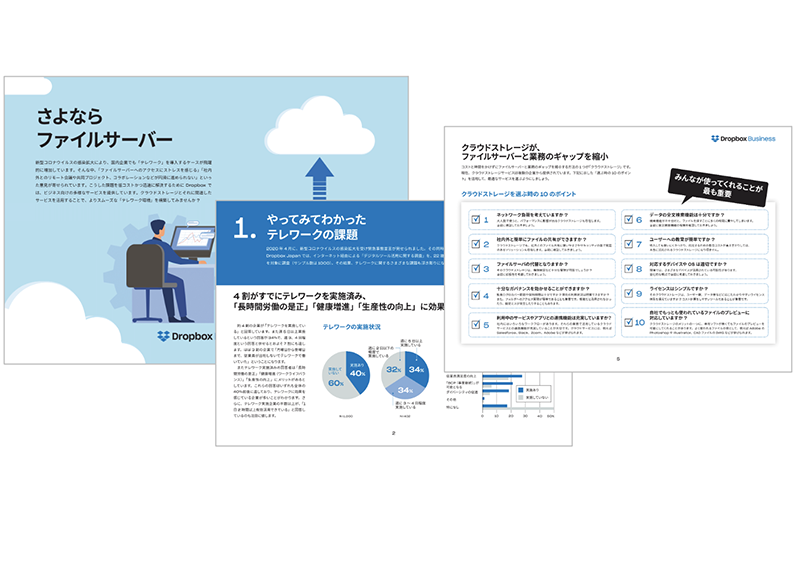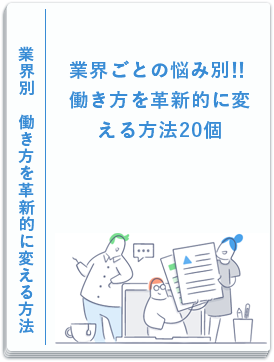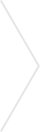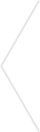1943 年、第二次世界大戦が激しさを増す中、マサチューセッツ工科大学(MIT)はレーダー開発計画の拠点となる新しい建物を必要としていました。計画立案者はヴァッサー ストリートの空地を選び、合板を使った間に合わせのバラックを建設しました。壁は薄く、雨漏りのするこの建物を消防署が使用禁止にしなかった唯一の理由は、大学側が建物の取り壊しを約束したからです。20 号棟(Building 20)と名付けられた仮設の建物は、後にチームのコミュニケーションに革命を起こすことになります。
終戦後、MIT はひそかに建物の使用目的を変更し、宇宙線研究所(原子力科学研究所の一部)、言語学科、粒子加速器、さらにはピアノ修理工場など、多岐にわたる借り手に場所を提供するようになりました。
20 号棟が特別な理由は、コミュニケーションと孤独が思いがけない形で共存していたことです。その輝かしい無秩序の歴史の中で 20 号棟がもたらしたものは、後に都市理論学者ジェイン・ジェイコブス氏の著書「都市の経済学(The Economy of Cities)」で「知識のスピルオーバー」と名付けられた無数のチャンスでした。
知識のスピルオーバーは、偶然の会話から分野の壁を越えてアイデアが流入するときに起こります。
20 号棟は十分な計画もないまま建設されたため、長年の入居者でさえ、存在すら怪しい部屋や階段を探して、当てもなく廊下を歩き回っていました。そして、この建物では 5 分歩き回る間に数十の異なる研究領域を通り抜け、同じ数だけの異なる会話が交わされるのが常でした。しかし、この建物には個別の研究室もあり、入居者はそこに引きこもって単独で作業することもできました。さらに、対外的には仮の建物であったため、大学からの援助対象とはならなかったものの、科学者や研究者は、建築基準法に多少違反したとしても、思いどおりの研究室を作ることができました。
それから 20 号棟は長年にわたってイノベーションのゆりかごとなり、最初の商用原子時計、重力波検出器、認知科学、そして世界初のビデオ ゲームを生み出しました。20 年という短い存続期間に、この建物の今にも崩れそうなドアから、9 人のノーベル賞受賞者が世に送り出されたのです。
20 号棟は、職場でのコミュニケーションや共同作業のモデルとなり得たはずです(実際にそうなるべきだったと主張する人もいます)。しかし 20 世紀にみられたのは、共有スペース、仕切りのないオフィス、常につながっていられるコミュニケーション スタイルへの移行でした。この「現代的な」コミュニケーションにはいくらかの価値があるものの、20 号棟のような場所にあったようなチャンスはありません。
目次
- 前時代的なコミュニケーション
- 妨害がもたらす危機
- 20 号棟の環境を再現
2-1. デイリー スタンドアップ
2-2. 非同期型コミュニケーション
2-3. リモート ワーク
2-4. ノーミーティング デー
1. 前時代的なコミュニケーション
2014 年 4 月、ある広告会社で私は初めての仕事に就きました。初出勤の日、職場のドアを開けた途端に、何とも言えない雑然とした物音に圧倒されたことを覚えています。電話が鳴り、大音量の音楽が流れる中、チームのメンバーがデスクを囲んで緊急会議を開いており、オフィスの両端から 2 人の顧客担当者が互いに怒鳴り合う声が聞こえてきます。
ほどなくして、このような激しいやり取りが普通だということを知りました。そこで働いていた当時は常に、別のプロジェクトで手が回らなくなった上司や同僚から作業を妨害されていました。集中できず混乱状態に陥った私は、人目につかないよう 10 分間で一気に仕事を片付けることを覚えました。
カル・ニューポート氏の生産性に関する著書では、これを「高負荷で場当たり的なワークフロー」と呼んでいます。「必要なときに声をかける。それこそが、この柔軟で体系化されていないコミュニケーションの取り方です」と同氏は説明しています。ニューポート氏によると、人間はこのコミュニケーション モデルを数千年もの間実践してきました。
旧石器時代、狩猟採集民族であった私たちの祖先が鹿を狩る必要に迫られたとき、彼らのコミュニケーション方法はいたって単純でした。部族の仲間を集め、鹿がいる方向を目指して出発し、歩きながら攻撃の計画を立てるのです。
この先史時代のコミュニケーション モデル(計画、調整、臨機応変なコミュニケーション)の驚くべき点は、現代の多くの企業で採用されているシステムと大して変わらないことです。私は最初の職場で、何か意見を求める必要があれば、上司のデスクまで歩いて行って質問していました。上司も同様に、必要なときはデスクまでやってきて私の仕事を中断し、互いに納得するまで話し合いました。
高負荷で場当たり的なワークフローは、先史時代の祖先にとっては有効でした。なぜなら、彼らのやり取りはテクノロジーの制約(正確にはテクノロジーがないという制約)があったからです。当時、部族の仲間に伝えたいことがあれば、自分から出向いていき、面と向かってやり取りする必要がありました。このような形のコミュニケーションはリソース消費型(実際にどこかへ出向く必要がある)であり、同期型(自分とコミュニケーションの相手がその場に居合わせる必要がある)です。
技術の進歩と共に、このようなやり取りにかかるコストは減少しました。手書きの書類は初の大きな進歩であり、相手が近くにいなくてもコミュニケーションが取れるようになりました。次の大きな飛躍は電話の発明で、遠く離れた場所にいる相手ともリアルタイムで通信できるようになりました。
技術の進歩によって、コミュニケーションの機会は爆発的に増加します。Bain & Company のパートナーであるマイケル・マンキンス氏によると、1970 年代に平均的な管理職のやり取りは年間 1,000 回(1 時間 47 分ごとに 1 回程度)でした。当時、ほとんどのコミュニケーションは書面と電話によるものであり、たまに対面でのミーティングも行われているという状況でした。
それからの 40 年間で、手紙と電話の両方をしのぐ新しいコミュニケーション ツールが数多く誕生しました。1990 年代に登場したメール、ポケットベル、携帯メールは、2000 年代には完全に定着し、個人や企業は考えたことを即座にメッセージとして送信できるようになりました。2010 年代には、Slack など多くのメッセージ アプリが開発され、メールや電話と共にどこでも利用可能になりました。2010 年代には、平均的な管理職は年間 3 万回(3.5 分ごとに 1 回程度)の連絡を受けるようになりました。
ニューポート氏は、高負荷で場当たり的なワークフローと最新技術の普及の組み合わせが、生産性に脅威をもたらすと考えていますが、これは実際のデータでも裏付けられています。通信速度が飛躍的に高まる一方で、生産性の伸びは立ち遅れています。実際、報告されている生産性向上率は年間 1.4 % に過ぎません。これは過去 30 年で最低の数値です。
2. 妨害がもたらす危機
最初の仕事に就いていたころ、私は TEDx でジェイソン・フリード氏(プロジェクト管理ソフト Basecamp の CEO)による「Why work doesn’t happen at work(なぜ職場で仕事がはかどらないのか)」というトークを見つけました。Basecamp はプロジェクト管理ツールを提供している企業ですから、きっと高度に最適化されたコミュニケーション システムを採用しているだろうと思ったのです。しかしそれは意外な内容でした。
オフィスに入ると 1 日がこま切れになります。こっちで 15 分、あっちで 30 分という具合に。そうしている間に別のことで仕事が中断され、それから 20 分後にはもう昼休みです。その後また別の仕事をしていると、15 分経った頃に誰かに話しかけられ、気づけばもう夕方。そして 1 日を振り返り、仕事が何一つ終わっていないことに気付くのです。
ー フリード氏
フリード氏の例が示すとおり、高負荷で場当たり的なワークフローはとてつもなく破壊的です。問題の一端は、人間の脳がタスクを切り替えられるようにできていないということです。現在やっている作業を中断すると、それまでの流れを取り戻すのに時間がかかります。カリフォルニア大学情報学部のグロリア・マーク教授によると、タスクを中断してから元のペースに戻るには 23 分 15 秒かかります。したがって、同僚のために仕事を 2 分間中断したら、25 分 15 秒もの時間を失うことになるのです。
中断による影響は甚大です。2010 年、米国の知識労働者は、作業の中断が原因で 1 日の労働時間の 28 %、つまり 2 時間 6 分もの時間を失っています。中断の問題を未解決のまま放置すると、2031 年までに労働時間の全体を占めることになると研究者は予測しています。しかし、実際に組織や企業がそこまでの状態になるとは考えられません。
労働者が慢性的な注意散漫の状態に陥るより先に、組織や企業が崩壊する可能性が高いからです。
2. 先史時代のコミュニケーションの改善
オープンな職場環境と継続的なコミュニケーションによる恩恵は計り知れません。偶然の出会いが思いがけない発想につながることもあります。そして同僚たちの話を聴く能力は、(気が散るというデメリットはあっても)全員が同じ認識を持ち、現在の目標に取り組む上で役立ちます。しかし、コミュニケーションの形は常に進化させてかなければなりません。これは私たちが先史時代のコミュニケーションと呼んでいるものについて、いくつかの代替案に目を向けることで実現できます。
2-1. デイリー スタンドアップ
最初の仕事はあまり長続きしませんでした。就職してわずか数日で自分に向いていないと感じた私は、早々に会社を辞めてしまいました。そしてマーケティング会社に再就職し、そこで働き始めた日に「スクラム」と呼ばれるアジャイル プロジェクト管理の手法が採用されていることを知りました。スクラムでは、プロジェクト全体を一気に計画するのではなく、プロジェクトを無数の小さな要素に分割します。それぞれの要素は、スプリントと呼ばれる一定期間内に設計、制作、納入を行います。
初出社の日、奇妙に静かなオフィスを案内してくれたマーケティング ディレクターは、アジャイルではコミュニケーションを重視するが、もっと重要なのはどんな形でコミュニケーションを取るかということだと説明してくれました。
翌日、私は彼女の言葉の意味を理解しました。私の所属するチームは毎朝午前 9 時 5 分きっかりに休憩室に集まり、デイリー スタンドアップという短いミーティングを開いていました。ミーティングでは、全員が 3 つの同じ質問に答えます。1 つ目は昨日行った仕事の内容。2 つ目は今日の予定。3 つ目は他のメンバーに頼みたいこと。
ミーティングが終わる頃には、複雑に絡み合った相関図が完成していました。ケビンは仕事を始める前にクライアントと契約を締結する必要があるので、エミリーに意思決定担当者への確認を頼みたい。ギャビンは自分の記事にグラフを載せたいと思っているので、時間があればナオミにグラフの作成を頼みたい。ウィルは最新版の広告コピーを受け取っていないので、メールで送ってもらえるようロスに頼みたい。
10 分の間に、その日発生するであろう仕事の中断が明らかになりました。ミーティングの直後、業務の滞りを解消するため、オフィス内がにわかに活気づきます。その後、午前 10 時 30 分頃から全員がようやく本来の仕事に取り組み始めました。丸 1 日分の仕事の中断が、1 時間ほどで一気に片付いたことになります。
デイリー スタンドアップではバッチ コミュニケーションについて暗黙の了解があり、そのおかげで物事が効率的に進みます。問題が生じても、すぐさま同僚に Slack で助けを求めることはできません。代わりに、次のスタンドアップまでその問題に集中します。かなり大きな行動の変化ですが、妨害を減らし、「ディープ ワーク」に費やす時間を確保する上で非常に効果があります。
スタンドアップといえば開発チームがするものというイメージがありますが、1 日のどこかで集中的にコミュニケーションを取りたいチームにはうってつけの方法です。アイデアを交換し、誰かが他の人の仕事で手一杯にならないようにするだけでなく、人々が集中モードに入り、有害な中断を回避するためのまとまった時間(勤務時間の大部分)を作る余裕が生まれます。
2-2. 非同期型コミュニケーション
誰かと対面または電話で話す場合、それは同期型コミュニケーションです。つまり、自分か相手のどちらかがいなければ会話は成り立ちません。一方、メールや Slack メッセージを送るとき、それは基本的に非同期型になります。自分が送ったメッセージに対する返事は、数分後に戻ってくるかもしれませんが、数時間後、あるいは数日後になるかもしれません。
ザック・ホールマン氏は 2011 年に書いた記事の中で、非同期型のメリットを見事に要約しています。ホールマン氏は、ある記事で非同期型コミュニケーションについて「昼食を食べに出かけ、戻ってきてから話の続きを文字で確認できることを意味する」と述べ、「チャットで同僚に質問でき、相手が都合のいいときに連絡をくれるだろうから迷惑をかける心配がない」としています。
ホールマン氏の見解には、非同期型コミュニケーションのメリットは両者にあるという含みがあります。会話を始める側は、相手の邪魔にならないかを心配することなく、いつでも助けを求め、会話を始めることができます。つまり、頭の中のアイデアが新鮮なうちに物事を進められます。そしてもちろん、メッセージを受け取る人にもメリットがあります。メッセージを確認しても、それまでやっていた仕事を終わらせてから応答することができます。
非同期型コミュニケーションが有効に働く理由の 1 つは、それがテクノロジーによって実現されている点にあります。誰かがあなたのデスクにやってきて質問をしたとき、その人を無視したらどのような気持ちになるか想像してみてください。生産性を維持するための行動だったとしても、職場の雰囲気は険悪になります。関係者全員が気まずい思いをすることは言うまでもありません。しかし、同じ質問をメールや Slack メッセージで受け取った場合は、生産性も職場の人間関係も維持することができます。
とは言え、私たちが使用するツールやテクノロジーは決して単純ではありません。たとえば Slack は非同期的(自分はメッセージを残し、相手は後で応答)にも、同期的(自分がメッセージを送ると相手がすぐに応答)にも使用することができます。このような場合、非同期型のユーザーが同僚を無視しているように見えるため、プラットフォームのユーザー間に敵対心が生じることがあります。
こうした状況を不快または無意味と感じるかもしれませんが、コミュニケーションに関して自分なりのルールを明確にすることは、チームにとっても非常に有用です。「このプラットフォームを全員で非同期的に使おう」と提案すれば、全員の認識を一致させ、以後のやり取りで同僚が不満を持つ可能性を最小限に止めることができます。
総合的に見て、非同期型コミュニケーションにはいくつか欠点があります。誰かが厳しい締め切りに追われていて、クライアントに今すぐ返事をする必要があるにもかかわらず、あなたが通知をオフにしていたらどうなるでしょうか?返事が遅れたせいで、事態が手遅れになってしまったら?このような理由から、完全な非同期型コミュニケーションだけでは不十分と言わざるを得ません。すべてのチームは、代替案としてビデオ通話や電話など、同期型の連絡手段を用意しておく必要があります。
非同期型のテクノロジーと同様、同期型の連絡手段の使用も体系化する必要があります。同期型の連絡手段に厳密な使用例を指定すれば、社員はそれらをデフォルトの連絡手段として使うことはなくなります。この方法であれば、非同期型コミュニケーションのメリットは守られます。
2-3. リモート ワーク
非同期型コミュニケーションに移行すると面白い現象が起こります。突然、実体としてのオフィスがそれほど重要ではないことに気づくのです。同僚からすぐに返事をもらう必要がなければ、同じ時間に働かなくても特に問題はありません。もっと言えば、同じ場所で働く理由もないのです。
その結果、過去 5 年間でリモート ワークは急速に増加しました。そして現在も、その傾向は続いているようです。The Work Foundation は、2020 年までに労働人口の 70 % 以上が部分的または完全にリモート ワークで働くようになると予測しています。
リモート ワークのメリットは計り知れません。Zapier の共同設立者であるウェイド・フォスター氏とマイク・ヌープ氏は、2011 年のスタートアップ設立時、従来型のオフィス環境について慎重でした。Zapier の共同創設者マイク・ヌープ氏は同社ブログのインタビュー記事で次のように述べています。
リモート以外の仕事では、最も気が散るコミュニケーション、つまり対面でのコミュニケーションがデフォルトで最優先されます。リモートワークは正反対で、最も気が散らないコミュニケーション、つまりコミュニケーションがない状態がデフォルトとなります。
リモート ワーカーにも作業の妨害や中断に対処しなければならないことはありますが、それでもオフィスに縛られている同業者に比べれば、そのような場面ははるかに少ないものです。フォスター氏によると、雑談に気を取られることがなく、「聴きたくない音楽を大音量で流す人もいないし、頭にボールをぶつけられることもない」としています。
リモート ワークでは、集中できない状況を自分で「選択」しない限り、誰かに押し付けられることはありません。Facebook を閲覧するにしても、Slack で会話をするにしても、それは自分の選択です。これで注意散漫や作業の中断が大幅に減ることになります。
これをヌープ氏は「気が散る原因が少なければ、作業が速まる」と端的に表現します。
もちろん、コミュニケーションの欠如がデフォルトであることで問題が生じる可能性はあります。たとえば、Zapier がチームのコアバリューを「透明性の確保」に設定したのは、その問題に対処するためです。Zapier では、このバリューをすべての社員に意識してもらうことで、たとえ非同期でも、必要なコミュニケーションがすべて従来どおりに行われるように徹底できています。もちろん、Zapier の社員は定期的にビデオ会議、電話、Slack による同期的なやり取りを行っています。繰り返しになりますが、要はバランスの問題です。
2-4. ノーミーティング デー
TEDx のトークで、フリード氏は現代のオフィスにおいて生産的な時間を確保するため、さらに過激な戦略を提案しています。
第一木曜の午後だけ、オフィス内の会話は一切禁止で、ひたすら沈黙を守ります。全員が誰とも会話しなければ、膨大な量の仕事が片付きます。これこそが本当に仕事ができる状況、つまり誰にも邪魔されず、作業を中断しなくてもいい状況です。4 時間連続して集中できる環境を作ることは、職場で働く誰にとっても最高のプレゼントです。
ー フリード氏
私は最近、Dropbox のコンテンツ担当グローバル責任者であるアレクサンダー・ムーアから、ある Dropbox チームが同様のアプローチを採用し、単独でディープ ワークを実行するためのまとまった時間を確保できるよう、「ノーミーティング デー」を導入した経緯について話を聞く機会がありました。
こうした時間を確保し、他の人に予定を入れさせないようにすることはとても難しいとムーア氏は言います。そこで、ムーア氏のチームは、ディープ ワーク専用の時間を確保するために勤務時間外のカレンダー イベントを作成することにしました。この時間帯に誰かが会議の予定を入れようとしても、Google カレンダーで自動的に拒否され、集中するための時間が確保されます。
Dropbox ではこれを『水曜日はノー会議デー(No Meeting Wednesdays)』と呼んでいますが、チームが希望し、しかるべき状況であれば、導入を奨励しています。社員にとって集中する時間は本当に充実したものであり、それを楽しみにしているようでした。もちろん、ほとんどの作業は最終的に共同作業ですから、Dropbox Paper のコメントであろうと、面と向かっての会議であろうと、その間は必然的に会話が増えることになります。
ー ムーア氏
3. 20 号棟の環境を再現
MIT の 20 号棟から生まれた革新、発見、発明の水準は、すべてのチームと組織にとっての目標です。私はムーア氏に対して、20 号棟の成功から何を学ぶことができるか、そして、それを現代の職場でどのように応用できるかについて意見を求めました。その答えは、すべてはバランスの問題というものでした。放任しすぎると、混沌とした先史時代のコミュニケーションによってチームに過度の負担がかかり、個人の生産性が低下します。ただしコミュニケーションの制限が厳しすぎると、組織にも悪影響を及ぼします。つまり、まったくコミュニケーションを取らないチームは、アイデアと創造性に欠けてしまうのです。
ムーア氏は、その中間のどこかに収まりの良いスポットがあると考えています。同氏はそれを、人々がコミュニケーションと集中のバランスを保てる「生産的緊張」の状態と表現しています。それは集中的に認識能力を働かせるのに十分な時間を確保するための場であるだけでなく、革新的発想と創造性を発揮するために欠かせない対人コミュニケーションで頭脳を活性化する場でもあるのです。